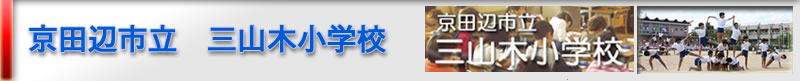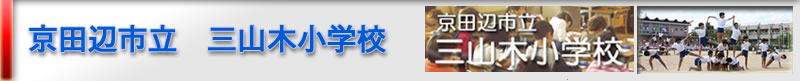| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
研究のテーマ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 子ども、教職員、保護者・地域がともに学び合い、育ち合う学校をつくろう |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究の経過と今年度の取り組み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17年度より研究のテーマを「子ども、教職員、保護者・地域がともに学び合い、育ち合う学校をつくろう」と設定し、研究、実践を進めてきた。授業研究として「学び合う授業の創造」をテーマに国語科、その中でも物語文、説明文を中心に研究を深めてきた。公開授業では、教科を絞らずに幅広く実践を進めてきた。また、基礎学力をつける取り組みでは、学力実態の分析をふまえ、朝学習、補習(基礎学力講座)、授業の中での取り組みなどさまざまな角度から学力の向上を図ってきた。さらに、保護者との連携では、授業や行事への保護者の参加、図書ボランティアなどの活動があった。また、言語環境の整備や児童の生活改善などの取り組みも行った。このように授業研究、基礎学力の充実、保護者との連携、環境整備など大きく3つに分けてテーマに迫った実践をしてきた。
しかしなお多くの課題が残っている。聴き合い、学び合う学びの仕方の獲得、基礎学力の充実および学力格差の是正、保護者・地域のさらなる学習参加、ボランティア活動、基礎的生活習慣の確立など多岐にわたっている。
こうした課題に挑戦するため、引き続き「学びの共同体」としての学校の創造に向けて全力を尽くすこととする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主な研究内容 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
学びあう授業の創造 |
国語科を中心として、他の教科でも |
2 |
基礎学力の充実 |
学力実態の分析と対策 |
3 |
保護者・地域との連携および教育環境整備 |
学習参加、ボランティア、基礎的生活習慣の確立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<研究組織>
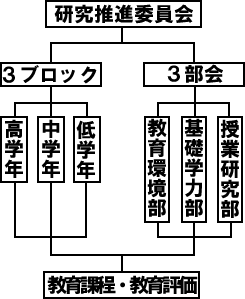
|
|
<授業研究部総括> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究授業・公開授業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5月19日 |
(金) |
公開授業 |
たんぽぽ |
算数・国語 |
| 6月14日 |
(水) |
公開授業 |
6-1 |
国語 |
| 6月23日 |
(金) |
公開授業 |
5-1 |
国語 |
| 6月28日 |
(水) |
研究授業 |
3-2 |
国語 |
| 6月29日 |
(木) |
公開授業 |
5-1 |
家庭科 |
| 11月1日 |
(水) |
研究授業 |
5-1 |
国語 |
| 11月7日 |
(火) |
公開授業 |
4-1 |
国語 |
| 11月22日 |
(水) |
研究授業 |
2-2 |
国語 |
| 12月8日 |
(金) |
公開授業 |
6-1 |
人権学習 |
| 1月29日〜31日 |
(月) |
公開授業 |
3-1 |
国語 |
| 2月15日 |
(木) |
(合同)公開授業 |
6年、1年 |
総合 |
| 3月2日 |
(金) |
公開授業 |
4-1 |
算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研修会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5月31日(水) |
模擬授業 |
詩「ゆき中の子犬」 |
| 8月24日(水) |
理論研修 |
国語科の系統指導 |
| 模擬授業 |
1年生物語教材「大きなかぶ」 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ア |
3つの研究授業と公開授業を実施する中で、お互いの教室を聞きあい、学びあうことができた。 |
|
|
イ |
学びあう授業のあり方についての形態や指導過程などに創意工夫が見られた。 |
|
|
|
・ |
座席をコの字型にして、お互いの顔を見ながら話し合う授業形態の工夫。 |
|
|
|
・ |
友達の意見を聞いて、自分の考えを変更したり、深めたりすることができた。 |
|
|
|
・ |
授業に対する児童の学びの姿勢がよくなり、教材に入り込み考えることができた。 |
|
|
|
・ |
児童の発言を中心にして研究会での議論が進んだ。その中で、教材解釈や授業の進め方、発問などについての議論が深まった。 |
|
|
|
・ |
教職員全体で児童一人ひとりを見ることができるようになってきた。 |
|
|
ウ |
教師の授業への意欲が高まった。 |
|
|
|
・ |
テーマに沿うための授業のあり方について意識的に実践できた。 |
|
|
|
・ |
教師個々の創意工夫が見られた。 |
|
|
|
・ |
教師間の信頼のもとに、学級を開くことができた。 |
|
|
|
・ |
理論研を行うことで、国語科の指導についての理解が深まった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
課題 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ア |
日常的な交流を通して、学び合う授業のイメージを明確にする。 |
| イ |
理論研や模擬授業などで、国語指導のあり方を深めていく。 |
| ウ |
学び合う授業を目指して、公開授業を広く行う。(特に算数科) |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
<基礎学力部総括> |
|
| |
|
|
|
|
朝学習 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
| 内容 |
朝礼
学級裁量 |
学級裁量 |
朝読書 |
学級裁量 |
算数 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ◎ |
集中して取り組める児童が多くなった。 |
| △ |
クラスの中に課題をやりきれない児童がいる。 |
| △ |
朝読書における教室内の本の充実が望まれる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
補習 |
|
「基礎学力講座」(4年生以上)の取組 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ・ |
算数を中心に各学年の課題である領域や内容を重点的に取り上げて行う。 |
| ・ |
クラスを解体し学年を3グループに分けて課題別に行う。 |
| ・ |
担任以外の教師も入り、できるだけ3人体制で行う。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
<教育環境部> |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
1 |
目標 |
|
| |
|
目で見て、耳で聴いて、声に出して、互いに学びあえる環境作りに努める。 |
| |
|
|
|
2 |
取り組み内容 |
|
| |
|
・教育環境の整備、望ましい保護者・地域との連携についての検討・実践(生活改善、ボランティア 等) |
| |
|
・「言語感覚を豊かにする」「学びあいを広げる」ための環境整備 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究のまとめ
|
|
|
|
|
|
|
「学び合い、育ち合う学校をつくろう」という理念のもと、3年目の研究となった。今年度も国語の研究授業を中心としながら、公開授業も実施してきた。また、基礎学力の充実を目指して朝学習や補習(基礎学力講座)にも力を入れた。さらに学習環境を整え、地域・保護者との連携を模索してきた。全体としては、着実に実践が進みつつあると考える。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|