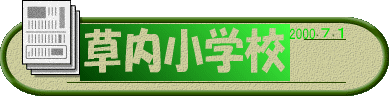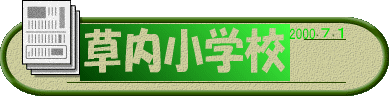カワニナのいる川
私たちの通っている草内小学校の近くには、カワニナのいる川があります。
カワニナは、タニシとはちがて、貝の部分をが、とんがっています。
カワニナは、ほたるの幼虫のエサになります。だから、その川の近くには、毎年ほたるがあわい緑色の光をはなちながら、飛び回っています。
カワニナは、草内地域の川にたくさんいます。カワニナがいる川は、水がきれいな証こです。
私たちが大人になっても、カワニナのいる、きれいな水であり続けてほしいです。


|
学校のじまん
私たちが通っている草内小学校は、今から110年以上も前にできた長い歴史がある学校です。
学校のそばには、法泉寺や咋岡神社があります。また、田んぼもまわりにたくさんあります。
児童数は340名です。たくさんの人が子ども郵便局で毎月貯金をしています。去年は子ども郵便局で郵政大臣から表しょうされました。
|
ほんのりした玉露
草内校区では、昔から玉露のさいばいがさかんです。手をかけた玉露の味は、しぶみがあり、あまみもあります。
有名な玉露は、飯岡で作られています。玉露は、黒い布をかけて日光が直接あたらないように作られています。
また、草内小学校では、ふるさと体験学習で、お茶つみをしました。
約5㎏のお茶をみんなでつみました。
6年生では「茶れんじタイム」で、お茶の学習もしています。
1度来て見学してください。 |
飯岡の七つ井戸って?
飯岡に昔からつたわる「七つ井戸」があります。 これらの井戸は、昭和3年から10年までの間に井戸組合が造ったと思われます。これらの井戸は水道が作られるまでずっと使われていたそうです。
この井戸のもとは、800年ごろ弘法大師が旅のとちゅうに飯岡に来て、ほらせたものだといわれています。井戸を探してみませんか?ガンバッテサガシテクダサイ!!
|
法泉寺においで
この法泉寺には、観音様や石塔神様があります。
観音様は、十一面観音といい、顔が11こあります。この十一面観音は草むらより出現され、草内の地名につながったと伝えられています。
十三重石塔は、鎌倉時代の1278年11月26日に建てられました。
これは、木津川のはんらんでなくなった人が成仏するように作られたものです。
もう1つは、お寺にはめずらしく、神様がまつられています。これは三宝荒神といいます。
また、法泉寺は、草内小学校のすぐとなりにあるので、ぜひ来てみください。
|
担任から
自分たちの校区や学校の良さを見つめ直す機会となりました。新しい発見もありましたね。
みんな意欲的に取材をしたり、記事を書いたりと、大変がんばりました。
編集委員
松山薫 三神裕也 長谷川沙織 岡本亜弓 谷村諒 古市裕美 岡本正人 杉田晃一
田畠遼 森田杏南 奥西美佳 井波千明
6−1担任 北脇眞須美 6−2担任 冨岡裕
|